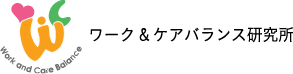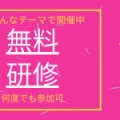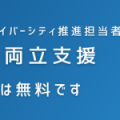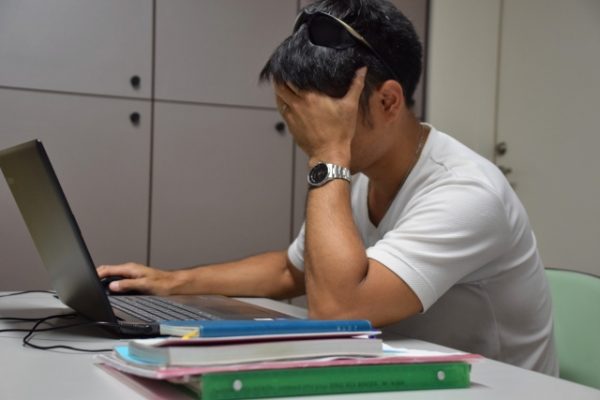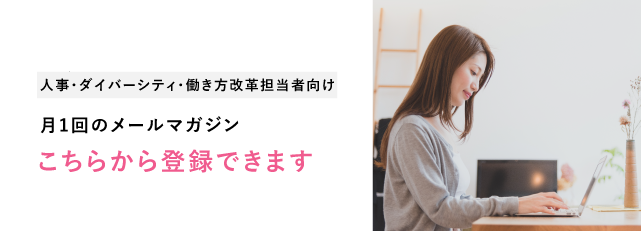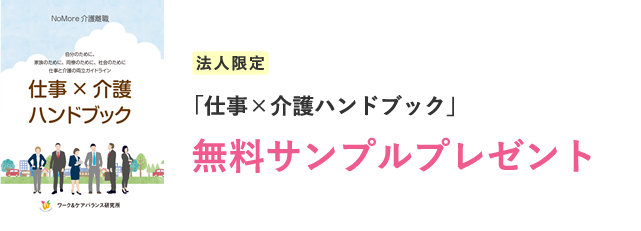仕事と介護の両立コラム 仕事と育児の両立支援の時に、介護休業制度等の説明はしていますか?|アンコンシャス・バイアスが周知を阻む

令和4年4月1日に妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置がはじまりました。
育児休業・出生時育児休業に関することが義務とされていて
短時間勤務制度や所定労働時間の制限などの制度の説明は義務ではありません。
当然、介護休業制度等の説明も義務ではありません。でも、本当は介護休業制度等の説明をした方が好ましいのです。
本記事では、仕事と育児の両立支援において介護休業制度等を説明した方がいい理由と、それを阻むアンコンシャス・バイアスについて解説します。

育児休業・出生時育児休業に関する制度の周知・意向確認の趣旨
育児休業を取得しやすい雇用環境づくりの一環として、妊娠・出産の申出があった場合は、個別の周知・意向確認が義務になりました。
周知・意向確認の内容は次のとおりです。
①育児休業・出生時育児休業(産後パパ育休)に関する制度
②育児休業・出生時育児休業(産後パパ育休)の申出先
③育児休業給付に関すること
④労働者が育児休業・出生時育児休業(産後パパ育休)期間に負担すべき社会保険料の取扱い
その上で、多くの会社では、復職後の子の病気等で利用できる「子の看護等休暇」や「短時間勤務」、「所定外労働の制限」等の、仕事と育児の両立のための多様な働き方の制度説明は復職前の復職支援面談の時に行っているようです。
企業によっては、妊娠・出産の申出があった時に、育児休業・産後パパ育休以外の制度も同時に説明している場合があります。
従業員としては妊娠時に申出をすることで育児系の制度の説明を一通り受けることは、育児との両立のイメージもつきやすいし、制度利用に伴う各種給付金の理解促進のためにも制度説明は大変ありがたい」と言う声もあるようです。周知・意向確認の方法としては、次の方法があります。
①面談
②書面交付
労働者が希望した場合に限り
③FAX
④電子メール でもよしとしています。

介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認
2024年の育児・介護休業法改正により、介護離職防止のために介護に直面した旨の申出があった場合は、個別の周知・意向確認が義務化になりました。
必要な時に、円滑に申出が行われるようにするための措置であることは育児休業等の周知目的と同じです。
育児休業等の周知義務と違う点は、周知しなくはいけない内容が介護休業のみならず、介護休暇等の介護両立支援制度も含まれることです。
周知・意向確認の内容は以下の通りです。
①介護休業に関する制度、介護両立支援制度等
②介護休業・介護両立支援制度等の申出先
③介護休業給付金に関すること
なお周知・意向確認の方法は育児休業の周知・意向確認と同様です。
育児休業等の対象家族と介護休業等の対象家族
育児休業は子を養育するためにする休業をいいます。
**************************************
労働者と法律上の親子関係がある「子」であれば、実子、養子を問いません。男性が事実婚の妻の子に対して育児休業をする場合には、申出時点において認知を行っていることが必要になります。
(引用:育児・介護休業法のあらまし)
**************************************
つまり、育児休業の対象家族は「子」です。
一方、介護休業は、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある対象家族を介護するためにする休業をいいます。対象家族の範囲は、次のとおりです。
●配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
●父母及び子(これらの者に準ずる者として、祖父母、兄弟姉妹及び孫を含む。)
●配偶者の父母
つまり「子」が「2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある」場合、介護休業制度の申請ができることがわかります。

仕事と介護の両立に対するアンコンシャス・バイアスが対策を偏らせる
ここまで制度の話をしてきましたが、ひとつ勘違いしないでほしいことがあります。
それは、「高齢化が進むなか、働く介護者が増えるから仕事と介護の両立支援をする」これでは、本来の介護離職防止並びに仕事と介護の両立支援にはならない点です。
いままでは多くのメディアがこの発想で仕事と介護の両立を取り上げていました。
しかし、現状、介護離職防止対策が進んでいません。理由は次の2つが考えられます。
①家族が介護に関わることが前提
②介護=高齢者とイメージをさせている
つまり、「家族が介護するのが当たり前」「うちの会社には介護に直面している人はいない」「うちの会社はまだ若い」という結論を導いていたためです。
そもそも介護離職防止並びに仕事と介護の両立は「少子高齢化で労働人口の減少を食い止めるために、離職の原因である介護離職を防止して、仕事と介護の両立を支援すること」です。
「高齢化が進むなか、働く介護者が増えるから仕事と介護の両立支援をする」との違いを、経営者や人事部にはしっかり理解していただきたいと思っています。
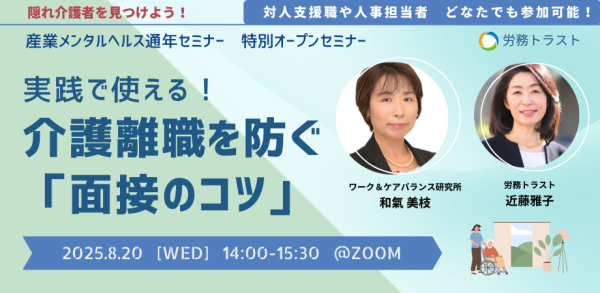
アンコンシャス・バイアス
経営者や人事部には、こういった介護や仕事と介護の両立等に対するアンコンシャス・バイアス(無意識の思い込み・偏見)に気づいてもらいたいところです。
しかし、アンコンシャス・バイアスだけに、なかなか難しいのも現実でしょう。
それゆえこのままでは介護離職防止対策が進まないので、この度の育児・介護休業法の改正において周知・情報提供を義務化したのです。
「介護離職はいつ起きるのか」を考えた時に、介護が始まって1か月未満に辞める人が約12%います。
つまり、介護がはじまったら直ぐに離職を選択している人もいることから、介護離職防止のための介護両立支援制度の早期情報提供を義務化しました。
また、対象家族の「常時介護を必要とする状態」においてはその判断基準の見直しもして、
「障害児・者や医療的ケア児・者を介護・支援する場合を含む。」とあえて明文化したのです。
今回の義務化は、仕事と介護の両立支援におけるアンコンシャス・バイアスを解消するためのものであり、企業はそれに務めるべきではないでしょうか。
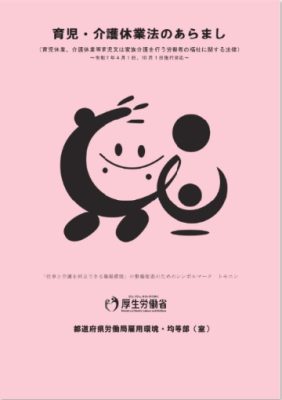
仕事と育児の両立におけるアンコンシャス・バイアスが周知を偏らせる
生まれてくるお子様に生活支援が必要な状態の場合もあります。出産時の事故で母体に介護が必要な障害が残ることもあるでしょう。
先日、私用で市役所に行った時に、隣の窓口に座って相談していた若夫婦は発達障害のあるお子様の相談をされていました。
ぱっと見ですが、30代前半のご夫婦でした。
「子供の障害について市役所に相談に行くから、会社を休む」時に、お子様の状態が2週間以上の期間にわたり常時介護が必要な状態であれば介護休暇が使えることを知っているのかな…などと思って、その場を去りました。
利用の有無は本人に任せつつ、周知徹底を
もちろん、制度を利用するかしないかは本人が決めればいいのです。知っているか知らないかが大きな問題なのです。
育児休業・出生時育児休業に関する制度の周知の時および仕事と育児の両立支援制度を説明する時には、介護休業制度並びに介護両立支援制度の説明も加えると、介護離職防止対策になります。
説明機会を作る、研修をする、リーフレットを配るなど、どうせ育児系の周知義務でやらなくてはいけないのです。手間は同じです。厚生労働省が作った各種リーフレットを配るだけでも十分です。ぜひ、貴社での「仕事と育児の両立支援」対策としてご検討ください。
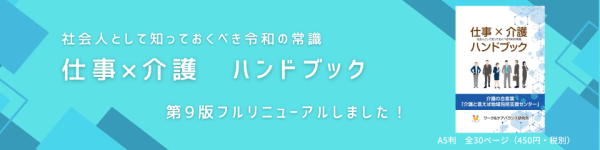
記事一覧
-
 仕事と介護の両立支援研修が今、企業に求められる理由|研修設計の工夫
仕事と介護の両立支援研修が今、企業に求められる理由|研修設計の工夫2026/02/01
-
 キャリア支援の一環としての仕事と介護の両立支援と位置づけ
キャリア支援の一環としての仕事と介護の両立支援と位置づけ2025/12/31
-
 仕事と介護の両立はコスト意識が要|気力・体力・お金・時間をコントロールする
仕事と介護の両立はコスト意識が要|気力・体力・お金・時間をコントロールする2025/11/30
-
 ダイバーシティ経営と仕事と介護の両立支援|声を聞き、声を出すことで企業価値を創ることの重要性
ダイバーシティ経営と仕事と介護の両立支援|声を聞き、声を出すことで企業価値を創ることの重要性2025/10/27
-
 あなたの経験が誰かのためになる|介護経験の共有の意義
あなたの経験が誰かのためになる|介護経験の共有の意義2025/09/29
-
 仕事と介護の両立支援において従業員から「親の介護をしたい」といわれたらどうしますか?企業に求められる対応のヒント
仕事と介護の両立支援において従業員から「親の介護をしたい」といわれたらどうしますか?企業に求められる対応のヒント2025/09/01
-
 有事に備えて地域包括支援センターまで散歩しよう|帰省と言うタイミングを何に使いますか?
有事に備えて地域包括支援センターまで散歩しよう|帰省と言うタイミングを何に使いますか?2025/08/03
-
 「知らなかった」ではすまない、働く介護者のリアル|知っておくべきセーフティーネット
「知らなかった」ではすまない、働く介護者のリアル|知っておくべきセーフティーネット2025/05/30
-
 介護をしていることは言いづらい?|周知意向確認の義務と従業員の心の内
介護をしていることは言いづらい?|周知意向確認の義務と従業員の心の内2025/05/05
-
 仕事と介護の両立が終わってもなお続く介護離職のリスク
仕事と介護の両立が終わってもなお続く介護離職のリスク2025/03/30
-
 介護離職はいつ起きる?|対話や会話で介護離職を防止する
介護離職はいつ起きる?|対話や会話で介護離職を防止する2025/03/04
-
 【改正育児・介護休業法】ミスリードにご注意ください!常時介護を必要とする状態に関する判断基準の見直し
【改正育児・介護休業法】ミスリードにご注意ください!常時介護を必要とする状態に関する判断基準の見直し2025/01/31
-
 【2025年】年始にはキャリアデザインを確認しましょう|100年時代の準備
【2025年】年始にはキャリアデザインを確認しましょう|100年時代の準備2025/01/05
-
 介護離職防止と仕事と介護の両立支援|当事者意識について考える
介護離職防止と仕事と介護の両立支援|当事者意識について考える2024/12/02
-
 仕事と介護の両立支援はキャリア支援です|キャリア面談のススメ
仕事と介護の両立支援はキャリア支援です|キャリア面談のススメ2024/10/31
-
 改正育児・介護休業法を活用しよう|「義務化」を上手に利用して働きやすい職場を作る
改正育児・介護休業法を活用しよう|「義務化」を上手に利用して働きやすい職場を作る2024/09/30
-
 突発事態に備えよう|介護休暇の使い方と今からできる備え
突発事態に備えよう|介護休暇の使い方と今からできる備え2024/09/02
-
 育児・介護休業の改正|それに伴う「事業主への措置義務」を考える
育児・介護休業の改正|それに伴う「事業主への措置義務」を考える2024/07/31
-
 介護者の不幸は選択肢が見えなくなること|仕事と介護の両立における選択の仕方
介護者の不幸は選択肢が見えなくなること|仕事と介護の両立における選択の仕方2024/06/26
-
 仕事と介護の両立支援の「周知対策」の秘訣|周知徹底する2つの方法
仕事と介護の両立支援の「周知対策」の秘訣|周知徹底する2つの方法2024/06/03