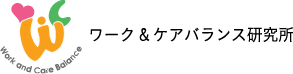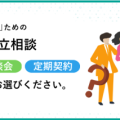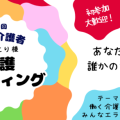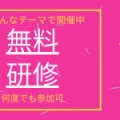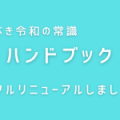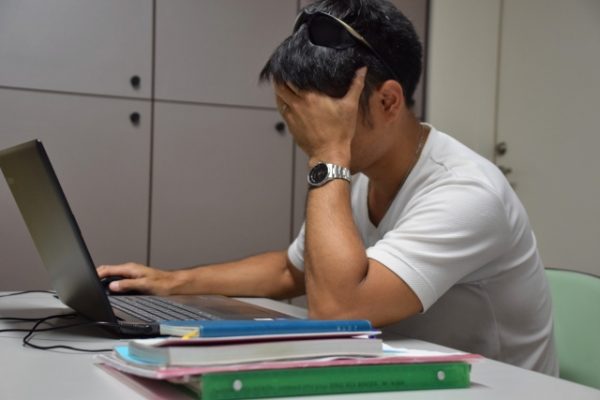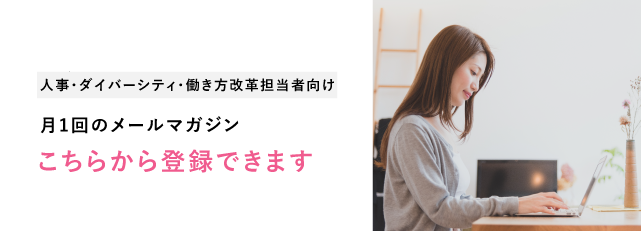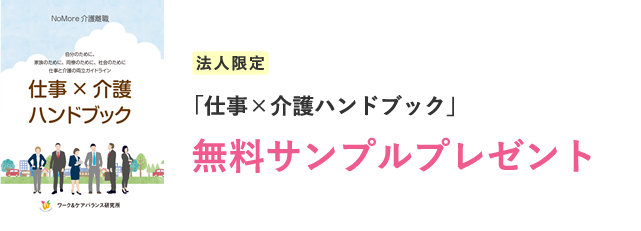仕事と介護の両立コラム あなたの経験が誰かのためになる|介護経験の共有の意義

2013年11月16日、私は「働く介護者おひとり様介護ミーティング」を立ち上げました。立ち上げ当初のキャッチフレーズは「貴女の経験が誰かを助ける」。
いまは「あなたの経験が誰かのためになる」と言い換えています。根本は変わりませんが、少しずつ変化している部分もあるのです。
今回は、介護経験を共有することの意義と、その際に忘れてはならない配慮について考えます。

きっかけ──“他の人はどうしているのだろう”
株式会社ワーク&ケアバランス研究所 代表取締役の和氣です。私は要介護5の母と暮らす現役の介護者で、介護が身近にある生活は20年を超えました。
突然の介護とわからないずくし
32歳のとき母が病気になり、わからないことだらけのまま、経済的な不安とも向き合いました。
病気が発症して、半年後に母は入院。「家族が入院する」という一大事に遭遇することが初めてで、母の病状はもちろん、お金はどうしたらいいのか、不安しかありませんでした。
入院から2週間で、特別な治療が必要とのことで、別の病院に転院することになりました。転院するには母を移送させなくてはいけません。
「救急車をだしてくれるのか?」と医者に聞けば「それはできない」といわれ、
「では、どうしたらいいのか?」と聞けば「自家用車か介護タクシーを使うよう」に提案される始末。
「介護タクシーとは何か?」という状態ではあるが、やるしかないのです。

消えない不安と初めての申請
病院の受付カウンターに並んでいる介護タクシーのパンフレットを片っ端から読み込み、手当たり次第電話して、なんとか移送を手伝ってくれる事業者を見つけることができました。
しかし、費用の不安は消えません。私も働いていましたから、当面のお金はあるとしても、このまま五月雨式に自分のお金が消えていくのかと思うと恐怖でしかありません。
そんな時に、国民健康保険のパンフレットを穴が開くほどみていたら、「移送費の支給」という制度を見つけたのです。目の前に一筋の光が見えた瞬間でした。
急いで市役所に電話をして手続きの方法を教えてもらい、申請書を取りに行き、その足で母の病院に制度の説明して、転院の日までに書類をそろえてもらうことにしました。
転院の日は、あわただしくて市役所に行く時間がなく、後日、改めて申請書を出しに行きました。ここまでで、移送費の申請のためだけに会社を2日間休んでいます。

却下の通知とみんなはどうしているのか
移送費の申請をしていたことを忘れかけていたある日、市役所から封書が届きました。移送費の支給についての可否です。
結果は「却下」。
理由は「緊急性がないため」とありました。
緊急事態だから、転院したのにもかかわらず「緊急性がないため」といわれたことに腹を立てた私は、翌日、会社を休んで異議申し立てに。同時に、市長に対して、ホームページからメールを出して「緊急性の定義を示してください」と伝えました。
翌日、市役所から電話があり「申請を許可するので、再度申請手続きをしてほしい」といわれることに。
「納得できないことを異議申し立てしたら、結果が変わる」という衝撃的な介護のスタートに「ほかの人はどうしているのだろう」という疑問が常に付きまとうようになったのです。
ちなみに、移送費の支給の手続きだけで、会社を4日休んでいます。これこそが私を今の仕事につかせた原体験です。
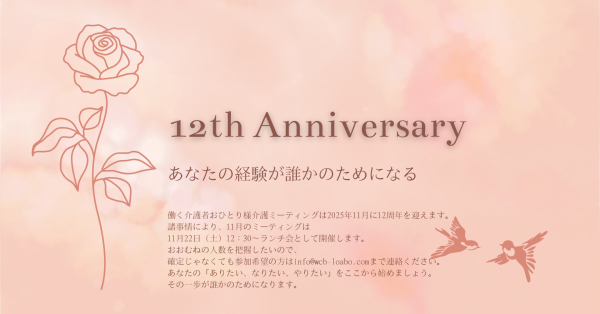
「おひとり様介護」との出会い、そして娘サロンへ
「ほかの人はどうしているのだろう?」という想いをかかえながらも、ほかの人がどこにいるのかわからず、病院が主催している「家族会」に一度参加したことがあります。
母が精神疾患だったので、病院の精神科が主催している家族会です。
しかし、その時の参加者のほどんどが「精神疾患のある子どもを療育している母親」。話も合わなければ、求めている情報も何もかもが違いました。それ以来「家族会」には足が遠のいていたのです。
2011年、母に認知症の診断が出たことや介護保険を使い始めたことで、再び「ほかの人はどうしているのだろう」という想いがこみあげてきました。
認知症といわれて、正直、毎日泣くほどのショックでした。救いを求めて立ち寄った本屋で『おひとり様介護』という本に出会いました。そこには、私と同じ体験をしている著者がいました。「私だけじゃないんだ!」と胸の底から安堵したことを今も覚えています。
同書で知った「親の介護をしている娘の会(通称:娘サロン)」に、群れるのが苦手な私が勇気を出して参加。
2年半ほど通う中で、「自分を助けてもらった介護者支援という考えを広めたい!」「自分の生涯をかけて介護者支援を広めたい」そして「働く介護者の声を社会に届けたい」という使命感が芽生えました。
これが、私が主催する「働く介護者おひとり様介護ミーティング」立ち上げのきっかけです。

立ち上げの試行錯誤と学び
もちろん、最初から上手くはいきませんでした。
参加者同士の意見の食い違い、否定や考えの押し付け、依存関係の芽生え、また主催者である私自身の感情移入……。
結果としてせっかく参加してくだった介護者に嫌な思いをさせてしまったこともあります。
私は他団体の会に足を運び、介護者の会のあり方やファシリテートを学びました。痛みを伴いながらも得た実感は、「介護経験者の語りは宝の山」だということ。
そして同時に、その宝は丁寧に扱わなければ容易に“消費”されてしまうということです。
経験は力、同時に守るべきもの
介護経験を語ることは、愛する家族の人生を語ることでもあります。
事実の語りを否定されたり、嘲笑されたりすることは、家族を貶められるのと同じ痛みを伴うものです。また介護経験を話すというのはつらい記憶がフラッシュバックする可能性もあります。
私自身、過去を詳しく語ることは得意ではありません。研修や講演では、自分語りは“スパイス”程度に留め、介護離職を防ぐための基礎知識や実用的な知恵を中心に据えています。経験の共有は「誰かのため」になる一方で、「語り手を守る」設計が不可欠です。

職場やイベントで「語り」を扱うときの指針
介護体験の共有の場を設けるにあたり、一番大事なことは目的を明確にすることです。
介護体験を聞くことで、自分事として考えてほしい、苦労話や語り手の想いに心を動かされ、結果として行動変容を起こしてほしいなどという場合は、語り手は外部の介護経験者を召喚しましょう。
結局はお涙頂戴の会になった時に、その語り手が社員である場合、語り手が職場でどのように思われるのかを考慮すべきです。
同じ会社の社員が仕事と介護の両立を頑張っている姿は、次の介護者にとって勇気になります。
例えば働く介護者としてのロールモデルとしてイベント登壇していたく場合は、まず語り手との合意形成が不可欠です。質疑応答などは極力避けるべきで、実施するのであればあらかじめ用意して差し上げるなどの配慮があったほうがいいでしょう。
最も大事なことは心理的安全性への配慮です。矢面に立つということは、賛辞を受けることだけではありません。時には批判的な言葉も浴びる可能性があることは語り手にお伝えしたうえで、主催者としても全力で守ってあげることが大事です。

例えば「否定はしないでください。自分の考え方と違ったとしても、そういう考え方もあるんだな、と受け止めましょう」というような参加者への参加姿勢に対する注意喚起があるといいでしょう。
また、介護経験者を囲んだ座談会なども、介護経験者同士のつながりができたり、情報交換や情報共有ができたりするので、場の運営によってはとても有意義な時間を作ることができます。
この場合、ファシリテーターが重要になるでしょう。
ファシリテーターは、まず終わりの時間を守ること。それゆえ、参加者が話すぎないように共有することが大事です。
また、アドバイスは求められたら自分語りとして回答するようにするといいでしょう。「こうしたほうがいいよ」というよりは「わたしはこうしたよ」という感じです。
注意すべきことは、介護未経験者から介護経験者への質問です。「たられば」の質問や興味本位な質問は介護経験者を傷つける可能性があるので、ファシリテーターとして先回りした回答をするなど、介護経験者の尊厳を守るようにしてください。
おわりに──“経験”を消費しない場づくりを
近年、介護経験者が登壇するイベントは増えました。発信できる人が発信することは大きな価値があるものです。一方で、企画・主催側には、語り手の尊厳と安全に最大限配慮し、「介護経験を消費しない」場づくりを強く求めます。
そして、2013年から試行錯誤しながら続けている介護者の会の経験は、きっと御社の力になると確信しています。社内介護経験者の経験共有の場づくりに興味のある企業様はぜひお問い合わせください。
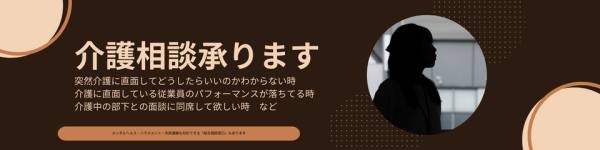
記事一覧
-
 仕事と介護の両立支援研修が今、企業に求められる理由|研修設計の工夫
仕事と介護の両立支援研修が今、企業に求められる理由|研修設計の工夫2026/02/01
-
 キャリア支援の一環としての仕事と介護の両立支援と位置づけ
キャリア支援の一環としての仕事と介護の両立支援と位置づけ2025/12/31
-
 仕事と介護の両立はコスト意識が要|気力・体力・お金・時間をコントロールする
仕事と介護の両立はコスト意識が要|気力・体力・お金・時間をコントロールする2025/11/30
-
 ダイバーシティ経営と仕事と介護の両立支援|声を聞き、声を出すことで企業価値を創ることの重要性
ダイバーシティ経営と仕事と介護の両立支援|声を聞き、声を出すことで企業価値を創ることの重要性2025/10/27
-
 仕事と介護の両立支援において従業員から「親の介護をしたい」といわれたらどうしますか?企業に求められる対応のヒント
仕事と介護の両立支援において従業員から「親の介護をしたい」といわれたらどうしますか?企業に求められる対応のヒント2025/09/01
-
 有事に備えて地域包括支援センターまで散歩しよう|帰省と言うタイミングを何に使いますか?
有事に備えて地域包括支援センターまで散歩しよう|帰省と言うタイミングを何に使いますか?2025/08/03
-
 仕事と育児の両立支援の時に、介護休業制度等の説明はしていますか?|アンコンシャス・バイアスが周知を阻む
仕事と育児の両立支援の時に、介護休業制度等の説明はしていますか?|アンコンシャス・バイアスが周知を阻む2025/06/30
-
 「知らなかった」ではすまない、働く介護者のリアル|知っておくべきセーフティーネット
「知らなかった」ではすまない、働く介護者のリアル|知っておくべきセーフティーネット2025/05/30
-
 介護をしていることは言いづらい?|周知意向確認の義務と従業員の心の内
介護をしていることは言いづらい?|周知意向確認の義務と従業員の心の内2025/05/05
-
 仕事と介護の両立が終わってもなお続く介護離職のリスク
仕事と介護の両立が終わってもなお続く介護離職のリスク2025/03/30
-
 介護離職はいつ起きる?|対話や会話で介護離職を防止する
介護離職はいつ起きる?|対話や会話で介護離職を防止する2025/03/04
-
 【改正育児・介護休業法】ミスリードにご注意ください!常時介護を必要とする状態に関する判断基準の見直し
【改正育児・介護休業法】ミスリードにご注意ください!常時介護を必要とする状態に関する判断基準の見直し2025/01/31
-
 【2025年】年始にはキャリアデザインを確認しましょう|100年時代の準備
【2025年】年始にはキャリアデザインを確認しましょう|100年時代の準備2025/01/05
-
 介護離職防止と仕事と介護の両立支援|当事者意識について考える
介護離職防止と仕事と介護の両立支援|当事者意識について考える2024/12/02
-
 仕事と介護の両立支援はキャリア支援です|キャリア面談のススメ
仕事と介護の両立支援はキャリア支援です|キャリア面談のススメ2024/10/31
-
 改正育児・介護休業法を活用しよう|「義務化」を上手に利用して働きやすい職場を作る
改正育児・介護休業法を活用しよう|「義務化」を上手に利用して働きやすい職場を作る2024/09/30
-
 突発事態に備えよう|介護休暇の使い方と今からできる備え
突発事態に備えよう|介護休暇の使い方と今からできる備え2024/09/02
-
 育児・介護休業の改正|それに伴う「事業主への措置義務」を考える
育児・介護休業の改正|それに伴う「事業主への措置義務」を考える2024/07/31
-
 介護者の不幸は選択肢が見えなくなること|仕事と介護の両立における選択の仕方
介護者の不幸は選択肢が見えなくなること|仕事と介護の両立における選択の仕方2024/06/26
-
 仕事と介護の両立支援の「周知対策」の秘訣|周知徹底する2つの方法
仕事と介護の両立支援の「周知対策」の秘訣|周知徹底する2つの方法2024/06/03