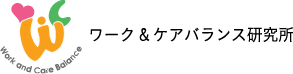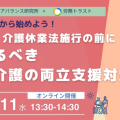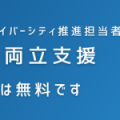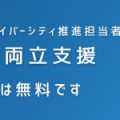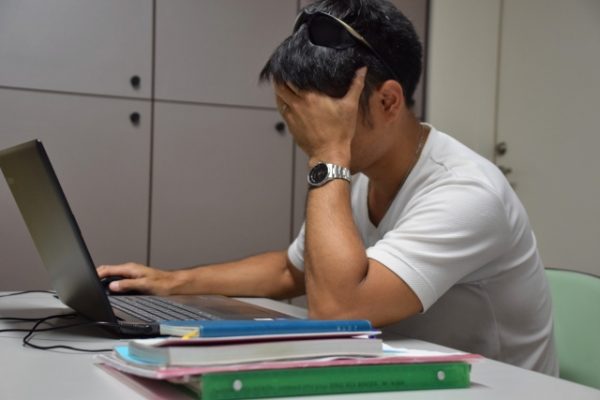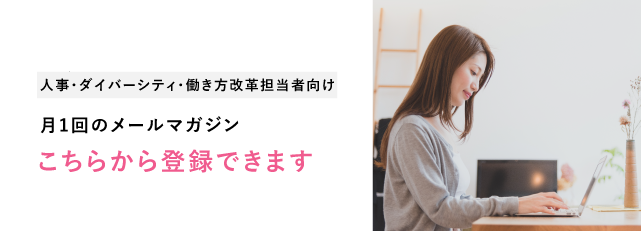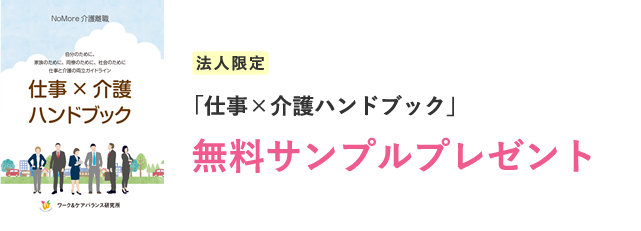仕事と介護の両立コラム 仕事と介護の両立支援において従業員から「親の介護をしたい」といわれたらどうしますか?企業に求められる対応のヒント

仕事をしながら家族の介護に関わっている人のことを「ワーキングケアラー」といいます。ワーキングケアラーには介護に関わらざるを得ない人と、介護に関わりたい人がいます。両者の違いをしっかりと理解しておかなければ、適切な判断を下せなくなってしまいます。
今回は、仕事と介護の両立を支援する現場できることを、一緒に考えましょう。

仕事と介護の両立とは
会社と労働契約を締結されている方には労働の義務があることを忘れてはいけません。
従って、会社に雇用されている従業員にとって仕事と介護の両立は労務提供義務を極力全うしながら、必要に応じて介護に関わることです。労務提供義務を全うしながらも、必要に応じて休みや一定期間の働き方を変えざるを得ないこともあります。
そんな時に使える権利が育児・介護休業法で規定されている制度を利用することです。
育児・介護休業法
一定の条件をクリアした従業員には、仕事と介護の両立をするために時間が必要な場合、育児・介護休業法で規定されている各種制度を利用できる権利があります。
育児・介護休業法とは、会社と労働契約を締結している従業員が子育てや家族の介護と仕事を両立できるよう、休業取得や短時間勤務などの利用に対しみなし労働とすることのできる法律です。
育児・介護休業法は拒否できない
事業主は労働者から制度申請等があった場合、雇用条件や労使協定による一定基準をクリアしていれば、それを拒否することはできません。つまり、育児・介護休業法に則った申請は、事業主側の都合で拒否できないのです。
従業員は労働基準法で規定されている年次有給休暇や、育児・介護休業法で規定されている介護休業制度等の法定休暇は「みなし労働」になります。法定休暇をつかうことは労務提供義務を全うしていることになるのです。
事業主は、この事実を頭に入れておく必要があるでしょう。
「家族の介護に関わることは当り前」ではない
「超高齢化社会に伴い、働きながら介護に関わる人は急増します」という文言が「介護が必要な家族が居る」ことを言い出せない一つの理由になっていることをご存知でしょうか。
「介護は家族がやるべきだ」という概念は、その「介護」が示す内容に幅があるとはいえ、多くの日本人の脳裏にある言葉のような気がします。実際、介護相談を受けていると「親の介護がはじまったら僕がやらなきゃいけないじゃないですか」と、親の介護に関わることを「前提」に相談してくる方は実に多いです。
この「前提」を暗黙の了解にしてしまうと「親の介護に関わりたくない」という想いのある方にとって、居心地の悪い環境をつくってしまいます。近年は「介護休暇の取得率を上げよう」というKPIを設定する企業もありますが、介護に関わりたくない、と思っている人にとっては「家族の介護のことを言ったら、『親不孝者!』とか『ご家族がかわいそう』などと思われそうだから、黙っておこう」と居心地の良くない環境になってしまいかねません。
大前提として、家族の介護に関わるか否かは社会が決めることではなく、当事者自身が判断するものです。では、介護に関わらざるを得ない従業員と、積極的に関わりたい従業員では、何が違うのでしょうか。
家族の介護に関わらざるを得ない従業員
従業員にとっての仕事と介護の両立において重要なことは、今の仕事に極力影響のない介護体制を作って維持継続することです。仕事と介護の両立は生活なので、状況に応じて臨機応変に対応することが求められます。介護に関わらざるを得ないケースの場合、特にこの体制を作り、維持していくことが重要です。
先にお伝えしておきますが、世の中には独居高齢者はたくさんいらっしゃいます。その方々が介護保険サービスを上手に活用できている現実から考えれば、家族の協力が無くても、その他のネットワークや福祉の力で介護体制の構築はできるのは周知のとおりです。
従業員のキャリア支援をしていると、子どもやきょうだい、配偶者や親の介護に、直接的または間接的に関わって、仕事と介護の両立をしている方に出会うことがあります。またいまは、そのような家族がいなくても、従業員の親のほとんどが将来的に介護が必要になることでしょう。そして、親に介護が必要になったとき、否応なしにそれに多少なりとも関わらざるを得ない従業員もいるのです。

家族の状況によって求める体制は変わってくる 要介護者の状況や要介護者の地域の状況によっては、従業員の生活に多大なる影響を及ぼす場合があります。
「要介護者の状態が不安定過ぎて介護体制が落ち着かない」ことを例としてあげましょう。介護サービスの利用の初期やガンの末期の時によくあります。こう言った場合、素人であるにもかかわらず、家族が要介護者のお世話に関わらざるを得ないことがあります。当然ながら、仕事に影響も出るのが現実です。
このように「仕事に集中するために、介護体制構築をしたいのだけれども、要介護者または周辺環境の兼ね合いで、直ぐに落ち着いた体制が整わない」ことはあります。
仕事に集中出来る環境を早く整えたいと思っている介護に関わらざるを得ない従業員にとって、介護体制が落ち着かない生活は精神的な不安を助長させてしまいかねません。結果、仕事でミスをしてしまうなど、悪循環になることも考えられるのです。

家族の介護に関わりたい従業員
家族の介護に関わりたくない従業員もいれば、家族の介護に関わらざるを得ない従業員もいます。そして、反対に家族の介護に関わりたいと希望する従業員もいます。
「家族の介護に関わりたい」と希望する従業員に対して、会社はどうしたらいいのでしょうか。
「家族の介護に関わりたい」と希望する従業員には「育児・介護休業法で規定されている制度を利用しながら、希望にあう休み方・働き方を話し合ましょう」がベストでしょう。従業員が制度の存在を知らない可能性があるからです。
一方で会社としては、「働き方を変えるとしてもどの程度の期間なのか」という見込みが欲しいのが本音でしょう。従って、法定内の働き方の変更で最短は3年です。そのため、3年間までであれば、従業員の希望を軸に職場運営をしていかざるを得ません。
しかし、介護はいつまで続くかわかりませんし、いつ終わるかもわからないのが現実です。3年間の間、職場運営を臨機応変に対応できるのであれば問題ありませんが、なかなかそのような職場は無いでしょう。
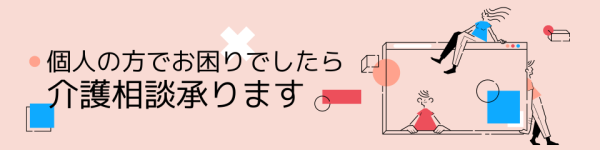
介護に関わる従業員に対する事業主の課題
仕事と介護の両立支援において、最も難しいのは職場運営です。
介護に関わらざるを得ない従業員/介護に関わりたい従業員、いずれも、職場としてはマンパワーが減る事に対しての懸念があります。「いつ、仕事に集中出来る環境が整うのか」「いつまで家族の介護を中心にして働くのか?」という「期間」が不明瞭なことが、会社にとって次のアクションを躊躇させる原因かもしれません。
しかし、繰り返しになりますが、介護はいつ終わるのか・いつまで続くかなどは誰にもわからないでしょう。当然、当該従業員も「いつまで」とは言えない状況にあります。そんな時は、「まずは半年(または3カ月)、働き方を変えてやってみよう。半年後にまた相談しよう」と、期限の提案をしてみるのはどうでしょう。

介護に関わる従業員の課題
従業員側から上司に相談するのであれば「介護体制が不安定で、仕事に集中出来る状態にありません。とはいえ、この状況が良いとも思っていませんので、善処はしますが、ひとまず、半年間の働き方を変えたい」や「介護に積極的に関わりたいのですが、その状況がいつまで続くかわかりません。なので、とりあえず半年間、働き方を変えたい」などと、権利の行使を主張するだけではなく、職場運営の懸念を一緒に考えることも大事です。
周辺の協力を仰げるように
そして、マンパワーが減る期間が明確になったのであれば、次にマンパワーを補う必要があります。当該従業員にも協力してもらって、当該従業員の仕事を分担できる人材を当該従業員と一緒に探してもらう、一緒に育ててもらうことなど、当該従業員には極力協力してもらいましょう。
それが、当該従業員が職場で働き続けるための居心地にも関係してくるからです。
介護に直面している従業員が働き方や休み方の相談をしてきたら、職場のことも一緒に考えてもらう、これが仕事と介護の両立支援のコツです。

記事一覧
-
 キャリア支援の一環としての仕事と介護の両立支援と位置づけ
キャリア支援の一環としての仕事と介護の両立支援と位置づけ2025/12/31
-
 仕事と介護の両立はコスト意識が要|気力・体力・お金・時間をコントロールする
仕事と介護の両立はコスト意識が要|気力・体力・お金・時間をコントロールする2025/11/30
-
 ダイバーシティ経営と仕事と介護の両立支援|声を聞き、声を出すことで企業価値を創ることの重要性
ダイバーシティ経営と仕事と介護の両立支援|声を聞き、声を出すことで企業価値を創ることの重要性2025/10/27
-
 あなたの経験が誰かのためになる|介護経験の共有の意義
あなたの経験が誰かのためになる|介護経験の共有の意義2025/09/29
-
 有事に備えて地域包括支援センターまで散歩しよう|帰省と言うタイミングを何に使いますか?
有事に備えて地域包括支援センターまで散歩しよう|帰省と言うタイミングを何に使いますか?2025/08/03
-
 仕事と育児の両立支援の時に、介護休業制度等の説明はしていますか?|アンコンシャス・バイアスが周知を阻む
仕事と育児の両立支援の時に、介護休業制度等の説明はしていますか?|アンコンシャス・バイアスが周知を阻む2025/06/30
-
 「知らなかった」ではすまない、働く介護者のリアル|知っておくべきセーフティーネット
「知らなかった」ではすまない、働く介護者のリアル|知っておくべきセーフティーネット2025/05/30
-
 介護をしていることは言いづらい?|周知意向確認の義務と従業員の心の内
介護をしていることは言いづらい?|周知意向確認の義務と従業員の心の内2025/05/05
-
 仕事と介護の両立が終わってもなお続く介護離職のリスク
仕事と介護の両立が終わってもなお続く介護離職のリスク2025/03/30
-
 介護離職はいつ起きる?|対話や会話で介護離職を防止する
介護離職はいつ起きる?|対話や会話で介護離職を防止する2025/03/04
-
 【改正育児・介護休業法】ミスリードにご注意ください!常時介護を必要とする状態に関する判断基準の見直し
【改正育児・介護休業法】ミスリードにご注意ください!常時介護を必要とする状態に関する判断基準の見直し2025/01/31
-
 【2025年】年始にはキャリアデザインを確認しましょう|100年時代の準備
【2025年】年始にはキャリアデザインを確認しましょう|100年時代の準備2025/01/05
-
 介護離職防止と仕事と介護の両立支援|当事者意識について考える
介護離職防止と仕事と介護の両立支援|当事者意識について考える2024/12/02
-
 仕事と介護の両立支援はキャリア支援です|キャリア面談のススメ
仕事と介護の両立支援はキャリア支援です|キャリア面談のススメ2024/10/31
-
 改正育児・介護休業法を活用しよう|「義務化」を上手に利用して働きやすい職場を作る
改正育児・介護休業法を活用しよう|「義務化」を上手に利用して働きやすい職場を作る2024/09/30
-
 突発事態に備えよう|介護休暇の使い方と今からできる備え
突発事態に備えよう|介護休暇の使い方と今からできる備え2024/09/02
-
 育児・介護休業の改正|それに伴う「事業主への措置義務」を考える
育児・介護休業の改正|それに伴う「事業主への措置義務」を考える2024/07/31
-
 介護者の不幸は選択肢が見えなくなること|仕事と介護の両立における選択の仕方
介護者の不幸は選択肢が見えなくなること|仕事と介護の両立における選択の仕方2024/06/26
-
 仕事と介護の両立支援の「周知対策」の秘訣|周知徹底する2つの方法
仕事と介護の両立支援の「周知対策」の秘訣|周知徹底する2つの方法2024/06/03
-
 研修を実施すれば仕事と介護の両立はできるのか|仕事と介護の両立の本質
研修を実施すれば仕事と介護の両立はできるのか|仕事と介護の両立の本質2024/05/01