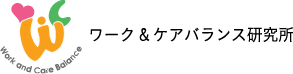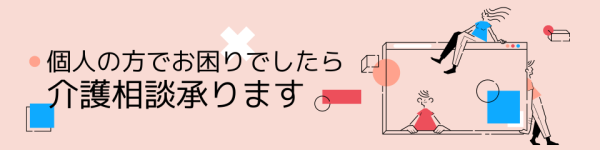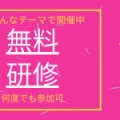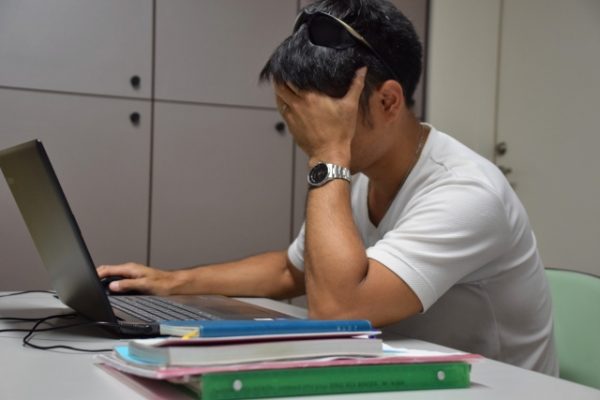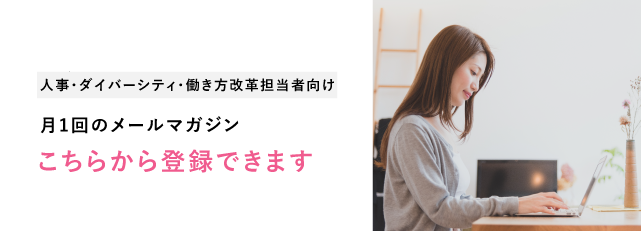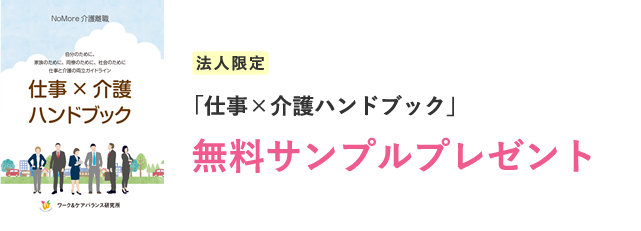仕事と介護の両立コラム 有事に備えて地域包括支援センターまで散歩しよう|帰省と言うタイミングを何に使いますか?

そろそろ夏休みが始まる企業も多いのではないでしょうか。夏休みのタイミングで「帰省」される方もいると思います。
ぜひ今年の夏休みの「帰省」時に、ご家族やご親族でやってもらいたいことがあります。それは、有事に備えた話し合いです。

「帰省」とは
「帰省」とは,
郷里に帰ること、郷里に帰って父母を見舞うことです。「郷里」はいまのお住まいよりも少し離れたところのように思われますが、祖父母や父母の住んでいるところを見舞うことであるため、距離は関係ありません。スープの冷めない距離でも、飛行機に乗っていく距離でも「帰省」です。
盆暮れ正月は少しまとまったお休みが取れることが多いため、「帰省」される方が多いのではないでしょうか。皆さんは「帰省」というタイミングを何に使っていますか?
近いから、遠いからではなく、ぜひ、「帰省」というタイミングでやってもらいたいことを紹介します。

備えあれば憂いなし
防災と介護は「備えあれば憂いなし」と言われることがあります。中国の書物に由来する言葉で「前もって準備していれば心配する必要はない」という意味です。「いつか来る」「突然来る」と言われていても、どこか現実身を帯びてないがゆえに、準備や備えを先送りにする傾向にありませんか?
日本の防災意識は、大規模災害の発生によって一時的に高まり、その後緩やかに薄れるというサイクルを繰り返す傾向にありました。いわゆる「喉元過ぎれば熱さを忘れる」という傾向です。
しかし、近年は地球温暖化の影響などによる自然災害の激甚化・頻発化、そして能登半島地震のような災害や南海トラフ地震の情報などに折に触れ、全体としては以前よりも高い水準で備えの意識が高まっているようです。

有事は突然やってくる
日本時間の7月30日午前8時25分ごろに起きた、ロシア極東のカムチャツカ半島沖を震源とする大規模な地震は皆さんの記憶に新しいのではないでしょうか。津波の影響で公共交通機関が一部不通になり、仕事でも遊びでも多くの方に影響がありました。
「夏休み」というタイミングでもあり、町も人も会社も行政も新たな角度をもった備えや準備の必要性を感じた人もいると思います。このように、有事は突然やってくるのです。
介護も有事とよく似ている
さて「有事」とは「国家や企業の危機管理において戦争や事変、武力衝突、大規模な自然災害などの非常事態を指す概念」とあります。介護は有事ではありませんが、いずれも「突然やってくる」という意味で個人単位・家庭単位での「備えや準備」という点においては共通点もあります。
いつやってくるかわからない介護に備え、有事と同じように用意をしておきましょう。

防災の備えと介護の備え
防災の備えと介護の備えの共通点とは何なのでしょうか。具体的には次のようなものです。
●備蓄品の準備
●安全な居住空間の確保
●情報収集と連絡体制
●訓練とシミュレーション
●地域の連携と支援体制
それぞれ詳しく見てみましょう。
備蓄品の準備
備蓄品は食料や水、衛生用品などが該当します。一般的に必要なものはもちろん、介護者にはさらに必要なものがあります。具体的には、以下のとおりです。
【食料・飲料水】
一般:災害時における最低3日~1週間分の食料と飲料水の確保
介護者:要介護者の嚥下能力(飲み込む力)や食事制限(アレルギー、糖尿病など)に配慮した、とろみ剤、流動食、やわらかいレトルト食品、経管栄養剤など
【衛生用品】
一般:トイレットペーパー、ティッシュ、ウェットティッシュ、生理用品、マスク、消毒液など
介護者:オムツ(大人用・子供用)、おしり拭き、ポータブルトイレ、介護用使い捨て手袋、口腔ケア用品(歯ブラシ、口腔ケアジェルなど)
【医療品・医薬品】
一般:絆創膏、包帯、消毒液など
介護者:処方されている常備薬(高血圧、糖尿病、心臓病など)、インスリンや吸入器などの医療機器とその電源・予備、持病に関する診断書や情報(お薬手帳など)
安全な居住空間の確保
居住空間の安全を確保しておくことも重要です。備品の準備はもちろんのこと、導線の確保もしておきましょう。
【家具の固定】
一般:家具転倒防止器具によるタンスや冷蔵庫などの固定
介護者:家具転倒防止器具によるタンスや冷蔵庫などの固定
【避難経路の確保】
一般:避難経路の確認と確保
介護者:車いすや歩行器での移動を想定した幅の確保、段差の解消、夜間でも視認できる誘導灯の設置など
【ライフライン停止への備え】
一般:電気、ガス、水道の停止に備え、懐中電灯、携帯ラジオ、カセットコンロ、電池など
介護者:医療機器を使用している場合は、ポータブル電源や予備バッテリー、電時でも使用できる充電式の簡易吸引器や、手動の痰吸引器などの確保
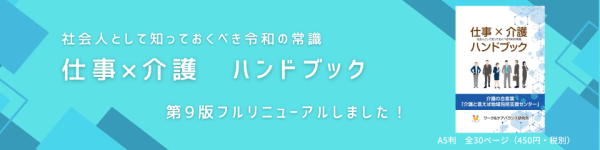
情報収集と連絡体制
災害時には、情報収集の手段や連絡できる体制を整えておく必要があります。具体的には次の対策を講じておきましょう。
【緊急連絡先の確認】
一般:家族や親戚、友人、職場の緊急連絡先のリスト化
介護者:かかりつけ医、ケアマネジャー、訪問看護・介護事業所、緊急時搬送先病院などの連絡先のピックアップ
【情報収集手段の確保】
一般:携帯ラジオ、予備バッテリー、モバイルバッテリーなど
介護者:情報伝達が困難な状況を想定し、地域住民やボランティアとの連携、安否確認の方法などを事前に取り決めておくこと
訓練とシミュレーション
万が一に備えて、防災訓練への参加をしましょう。自治体や地域で行われる防災訓練に積極的に参加し、災害時の行動を確認してください。
介護の視点では、要介護者の避難を想定した訓練(車いすでの避難、抱きかかえての避難など)を具体的に行い、課題を洗い出すことが重要です。また、避難場所までの経路や、避難所での生活をシミュレーションするのもいいでしょう。
地域の連携と支援体制
災害時に必要なもののひとつとして、地域連携が挙げられます。近隣住民との関係構築や、福祉避難所の場所を確認しておきましょう。
【近隣住民との協力】
一般:近隣住民との日頃からの交流
介護者:地域住民にその状況を伝えておくことで、災害時の安否確認や避難誘導において協力が得られやすくなります。またエレベータ―が停止した場合の下階への移動をふくめたマンション、アパートからの避難については、町内会やマンションの管理組合などを含めて話し合いをしておく必要もあります。
【福祉避難所の把握】
一般:指定避難所の場所や機能を把握しておく
介護者:高齢者や障害者など特別な配慮が必要な人が利用できる「福祉避難所」の場所や、受け入れ態勢を確認しておくこと
帰省と防災をきっかけに「介護」の備えを始めよう
介護の準備で最も大事なことは、家族親族でそれぞれの将来について「ありたい、なりたい、やりたい」を共有しておきましょう。
「介護状態になったらどうする?」ということだけではなく、もちろん、それも大事なことなのです。しかし、一番大事なことは「会話をすること」です。当然ながら「介護に関わりたくない」と思う家族もいるだろうし、自分が介護を受けることをイメージ出来ない家族もいるかもしれません。それも含めて言葉にして共有できたら理想です。
さらに理想を言えば、それぞれの将来の「ありたい姿、なりたい仕事、やりたいこと」を共有しましょう。自ずとお金のことや命のことに触れることにもなりますし、それぞれがそれぞれを応援しようと思えるかもしれません。
人間は誰しも必ず年を取ることを、子どもや孫やきょうだい、親、祖父母、みんなで共有することは命の授業でもあります。今年は戦後80年ですから、戦争の話から命の話、介護の話、将来の話をする、そんな会話もいいかもしれないです。
介護や命の話はなかなかできないのであれば前項の「防災の備え」という行動をすることで、言葉にしなくても準備をすることはできるかもしれません。福祉避難所や地域包括支援センターの場所を確認しながら家族で夕涼み散歩してきてください。
記事一覧
-
 仕事と介護の両立支援研修が今、企業に求められる理由|研修設計の工夫
仕事と介護の両立支援研修が今、企業に求められる理由|研修設計の工夫2026/02/01
-
 キャリア支援の一環としての仕事と介護の両立支援と位置づけ
キャリア支援の一環としての仕事と介護の両立支援と位置づけ2025/12/31
-
 仕事と介護の両立はコスト意識が要|気力・体力・お金・時間をコントロールする
仕事と介護の両立はコスト意識が要|気力・体力・お金・時間をコントロールする2025/11/30
-
 ダイバーシティ経営と仕事と介護の両立支援|声を聞き、声を出すことで企業価値を創ることの重要性
ダイバーシティ経営と仕事と介護の両立支援|声を聞き、声を出すことで企業価値を創ることの重要性2025/10/27
-
 あなたの経験が誰かのためになる|介護経験の共有の意義
あなたの経験が誰かのためになる|介護経験の共有の意義2025/09/29
-
 仕事と介護の両立支援において従業員から「親の介護をしたい」といわれたらどうしますか?企業に求められる対応のヒント
仕事と介護の両立支援において従業員から「親の介護をしたい」といわれたらどうしますか?企業に求められる対応のヒント2025/09/01
-
 仕事と育児の両立支援の時に、介護休業制度等の説明はしていますか?|アンコンシャス・バイアスが周知を阻む
仕事と育児の両立支援の時に、介護休業制度等の説明はしていますか?|アンコンシャス・バイアスが周知を阻む2025/06/30
-
 「知らなかった」ではすまない、働く介護者のリアル|知っておくべきセーフティーネット
「知らなかった」ではすまない、働く介護者のリアル|知っておくべきセーフティーネット2025/05/30
-
 介護をしていることは言いづらい?|周知意向確認の義務と従業員の心の内
介護をしていることは言いづらい?|周知意向確認の義務と従業員の心の内2025/05/05
-
 仕事と介護の両立が終わってもなお続く介護離職のリスク
仕事と介護の両立が終わってもなお続く介護離職のリスク2025/03/30
-
 介護離職はいつ起きる?|対話や会話で介護離職を防止する
介護離職はいつ起きる?|対話や会話で介護離職を防止する2025/03/04
-
 【改正育児・介護休業法】ミスリードにご注意ください!常時介護を必要とする状態に関する判断基準の見直し
【改正育児・介護休業法】ミスリードにご注意ください!常時介護を必要とする状態に関する判断基準の見直し2025/01/31
-
 【2025年】年始にはキャリアデザインを確認しましょう|100年時代の準備
【2025年】年始にはキャリアデザインを確認しましょう|100年時代の準備2025/01/05
-
 介護離職防止と仕事と介護の両立支援|当事者意識について考える
介護離職防止と仕事と介護の両立支援|当事者意識について考える2024/12/02
-
 仕事と介護の両立支援はキャリア支援です|キャリア面談のススメ
仕事と介護の両立支援はキャリア支援です|キャリア面談のススメ2024/10/31
-
 改正育児・介護休業法を活用しよう|「義務化」を上手に利用して働きやすい職場を作る
改正育児・介護休業法を活用しよう|「義務化」を上手に利用して働きやすい職場を作る2024/09/30
-
 突発事態に備えよう|介護休暇の使い方と今からできる備え
突発事態に備えよう|介護休暇の使い方と今からできる備え2024/09/02
-
 育児・介護休業の改正|それに伴う「事業主への措置義務」を考える
育児・介護休業の改正|それに伴う「事業主への措置義務」を考える2024/07/31
-
 介護者の不幸は選択肢が見えなくなること|仕事と介護の両立における選択の仕方
介護者の不幸は選択肢が見えなくなること|仕事と介護の両立における選択の仕方2024/06/26
-
 仕事と介護の両立支援の「周知対策」の秘訣|周知徹底する2つの方法
仕事と介護の両立支援の「周知対策」の秘訣|周知徹底する2つの方法2024/06/03