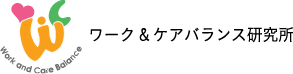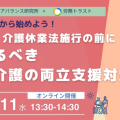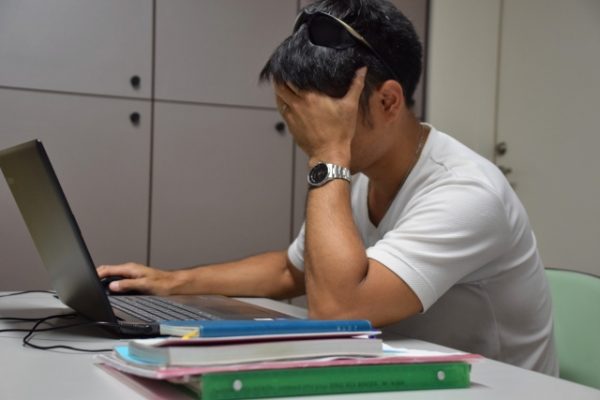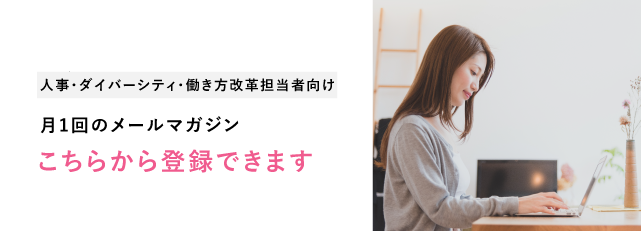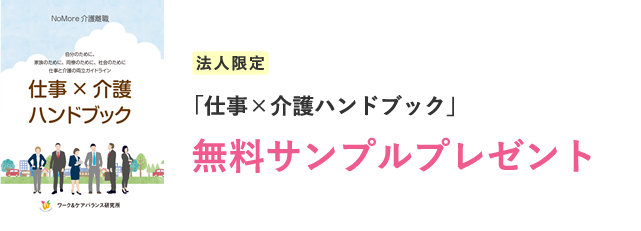仕事と介護の両立コラム 介護をしていることは言いづらい?|周知意向確認の義務と従業員の心の内

「介護をしていることは言いづらいのではないか?」と、そんな質問や相談を受けることがあります。介護に関わっていることを言いづらい理由はそれぞれですが、ひとつだけ言えることは、「あなたにも原因があるのでは?」という話です。
今回は、介護に直面していることを言いづらいという原因について深掘りしてみましょう。

介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の義務
2024年4月から、育児・介護休業の改正により、労働者から介護に直面した旨の申出があった場合、事業主は介護両立支援制度等の周知を行い、各制度の申請や利用について意向確認をしなくてはならなくなりました。これが個別の周知・意向確認義務です。
この改正の前から、経営者や人事部から「介護に直面した旨の申出って、あるのですか?」という質問を受けることがあります。逆に、経営者や人事総務担当者に「介護に直面した旨の申出を過去に受けたことはありますか?」と伺うこともあります。
前者においては「介護に直面したら報告してください」と周知しなければ、オフィシャルな申出はないでしょう。後者においては「過去に介護休暇や、介護離職の申出があったことはあります。」「オフィシャルに報告があったわけではありませんが、介護している従業員のことはなんとなく知っています。」という声はあります。
これらのことからわかるのは「介護に直面した旨の申出」を会社・経営者が受けるには、以下の3つの観点が必要だと考えています。
・「介護に直面したら申し出てください」と周知する必要がある
・介護両立支援制度の申請等があった場合を「介護に直面した旨の申出」とみなす
・介護に直面している人を知った時点で介護両立支援制度の周知意向確認をする必要がある
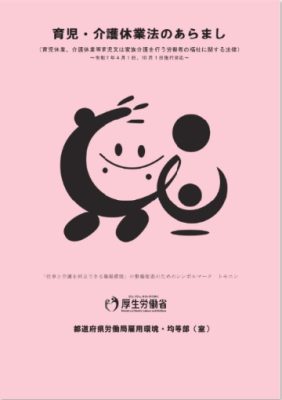
「介護に直面したら申し出てください」と周知する意味
このたびの法改正は、介護両立支援制度を知らないまま、または利用しないまま介護離職するケースを防ぐための対策です。そのために、介護に直面した旨を申出をした労働者に対しては、本人が介護両立支援制度を知っている・知らないに関わらず、制度等を周知し、その申請等に対する意向確認をすることで「使ってもいい制度」なのだという認識を労使共に改めて確認する機会とするのです。
と、理屈はわかったとしても、果たして従業員自ら「介護に直面しました」と報告するでしょうか。
恐らく、「介護に直面したことを報告する」という考え方がなければ、介護に直面した旨の申出をしようとは思わないないでしょう。そのため、何らかの形で「介護に直面したら●●まで申し出てください」ということを周知する必要があるのです。
しかし、そのようなルールが耳に届いたとしても、従業員は果たして報告してくれるのかと言われれば、そうでもありません。
「介護に直面しています」とは言いづらいのでは?
仮に、法改正に伴って「介護に直面したら●●まで申し出てください」という社内ルールを作ったとしましょう。それで本当に従業員は「介護に直面しています」と言いやすくなるのか?という疑問が残るかもしれません。その原因を探っていきましょう。
従業員が言えない理由を深堀する
では、あなたは『なぜ「介護に直面しています」と言いづらいのではないか』と思ったのでしょうか?主な理由としては、次のようなものが考えられます。
・家庭のことだからですか?
・育児は何となくおめでたいことだけど、介護は終りが見えないし、つらそうだからですか?
・評価に影響がでるのではないかと思っているからですか?
・職場に迷惑が掛かると思っているからですか?
介護に直面している従業員に「言いづらい理由」を聞いたわけではないのに、勝手に想像して「●●だろう」と、決めつけていることはしていませんか。実際に聞いてみなければわからないことを、あえて予想する必要はありません。

あなた自身が言いづらい原因を作っている可能性も
もし、あなた自身が「介護に直面していることは言いづらいです」と思うのであれば、言いづらくしている一因をあなたも担ってきた可能性はあります。
あなた自身が介護に直面する前、もしかしたら今のあなたが介護に直面した同僚が部下を目の端で捉えたとき、あなたはもしかしたら知らず知らずのうちに「メンドクサイな」とか「可哀想だな」とかいう雰囲気を意図せず醸し出しているかもしれません。または醸し出していたかもしれないのです。
介護に直面すると、妙に周りの目が気になることがあります。こういった「雰囲気」というものは当事者にならないと気づかない・感じないものなのです。いざ当事者になってみると、自社の風潮として言いづらいのか否かがよくわかるでしょう。
だからといって「当事者意識を持ちましょう!」と、性善説を唱えるつもりはありません。「介護に直面しています」と言いづらい雰囲気を作ってきたのは「介護」に対する考え方や、「介護」が持つイメージがそうさせてきただけであって、これは時代と共に変わっていくことです。
あなたの会社のなかの誰かが仕事と介護の両立の最初の一歩を踏み出してくれることで変わっていきます。その最初の一歩に自分がなるか、だれかを待つかはあなた次第です。

「介護に直面しています」と言わないといけないのでしょうか?
そもそも従業員は、いちいち会社に「介護に直面しています」と言わなくてはいけないのでしょうか。たしかに今回の改正で「介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の義務」はありますが、「介護に直面した旨を申し出ましょう」とは言っていません。
会社側が報告してほしいと思う理由
では、介護に直面していることを報告して欲しい、会社としての理由は何でしょう。以下のことが考えらえると思います。
・介護離職を防止したい
・介護両立支援制度の情報提供をしたい
・仕事と介護の両立支援をしたい
・誰もが長く働ける職場を作りたい
会社としては、介護に直面していたとしても、簡単に離職されては困るケースもあるでしょう。それを未然に防ぐための対策を講じるためには、従業員からの報告が必須なのです。そのような意味で、会社側は介護に直面している事実を報告してほしいと考えています。
従業員側が会社に報告することで得られるメリット
しかし、あくまでこれは会社側の理由です。従業員の立場として介護に直面したことを報告しておいた方がいい理由は何でしょうか。私は次のようなメリットがあるからだと考えています。
・働き方を変えやすくなる
・休みやすくなる
・職場の協力を得やすくなる
つまるところ「働きやすくなる」「仕事と介護の両立がしやすくなる」ということだと思います。
従業員が仕事と介護の両立をしやすくするために、介護両立支援制度の利用申出をした場合、それは「介護に直面した旨を申し出た」ことに相違ないです。会社は従業員の介護離職を防止したいのであれば、この機会を「周知・意向確認の義務」の実施と捉えるべきです。
介護に直面したことを言い出しにくいのではなく、実はすでに言っていることに気づいてほしいです。
非公式な「介護に直面している旨」
人づてでも、普段の会話の流れのひとコマでも、従業員が「介護に直面している旨」の情報をキャッチしたら、お節介にも周知・意向確認の情報も含めた情報提供から始めて欲しいと思います。介護離職防止の基本は、まずは「情報提供」です。その上で、オフィシャルな「介護に直面した旨の申出」があれば周知・意向確認をおこないましょう。
しかし現場では『●●ハラスメント』『個人情報保護』が気になって、お節介がしづらい、なんていう声も届きます。お節介がしづらいのであれば無理にする必要もありません。非公式な「介護に直面している旨」の申出であるため、周知・意向確認の義務には該当しないからです。
会社に言いたくない人の力になるには?
もしその方が仕事と介護の両立に真剣に悩んでいるのであれば、それは上司や同僚として真摯に対応して欲しいのです。その対応の延長で「介護に直面した旨の申出をすると、社内の制度の案内なんかをしてくれるようだよ」と情報提供してもらえればいいのではないかと思います。
そのような上司や同僚のお節介に対して「介護に直面していることは言いたくない!」というのであれば、それは仕方ありません。しかも、仕事に支障をきたしていないのであれば会社も文句は言わないです。問題は、「介護に直面していることは会社に言いたくない」かつ「仕事に支障が出ている」場合でしょう。
そのような方がおられましたら、そっと、ケアラーズコンシェルをご紹介ください。
弊社は個人から直接の仕事と介護の両立相談も承っています。
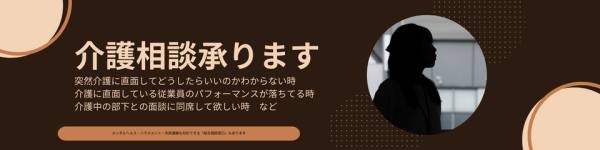
記事一覧
-
 仕事と介護の両立支援研修が今、企業に求められる理由|研修設計の工夫
仕事と介護の両立支援研修が今、企業に求められる理由|研修設計の工夫2026/02/01
-
 キャリア支援の一環としての仕事と介護の両立支援と位置づけ
キャリア支援の一環としての仕事と介護の両立支援と位置づけ2025/12/31
-
 仕事と介護の両立はコスト意識が要|気力・体力・お金・時間をコントロールする
仕事と介護の両立はコスト意識が要|気力・体力・お金・時間をコントロールする2025/11/30
-
 ダイバーシティ経営と仕事と介護の両立支援|声を聞き、声を出すことで企業価値を創ることの重要性
ダイバーシティ経営と仕事と介護の両立支援|声を聞き、声を出すことで企業価値を創ることの重要性2025/10/27
-
 あなたの経験が誰かのためになる|介護経験の共有の意義
あなたの経験が誰かのためになる|介護経験の共有の意義2025/09/29
-
 仕事と介護の両立支援において従業員から「親の介護をしたい」といわれたらどうしますか?企業に求められる対応のヒント
仕事と介護の両立支援において従業員から「親の介護をしたい」といわれたらどうしますか?企業に求められる対応のヒント2025/09/01
-
 有事に備えて地域包括支援センターまで散歩しよう|帰省と言うタイミングを何に使いますか?
有事に備えて地域包括支援センターまで散歩しよう|帰省と言うタイミングを何に使いますか?2025/08/03
-
 仕事と育児の両立支援の時に、介護休業制度等の説明はしていますか?|アンコンシャス・バイアスが周知を阻む
仕事と育児の両立支援の時に、介護休業制度等の説明はしていますか?|アンコンシャス・バイアスが周知を阻む2025/06/30
-
 「知らなかった」ではすまない、働く介護者のリアル|知っておくべきセーフティーネット
「知らなかった」ではすまない、働く介護者のリアル|知っておくべきセーフティーネット2025/05/30
-
 仕事と介護の両立が終わってもなお続く介護離職のリスク
仕事と介護の両立が終わってもなお続く介護離職のリスク2025/03/30
-
 介護離職はいつ起きる?|対話や会話で介護離職を防止する
介護離職はいつ起きる?|対話や会話で介護離職を防止する2025/03/04
-
 【改正育児・介護休業法】ミスリードにご注意ください!常時介護を必要とする状態に関する判断基準の見直し
【改正育児・介護休業法】ミスリードにご注意ください!常時介護を必要とする状態に関する判断基準の見直し2025/01/31
-
 【2025年】年始にはキャリアデザインを確認しましょう|100年時代の準備
【2025年】年始にはキャリアデザインを確認しましょう|100年時代の準備2025/01/05
-
 介護離職防止と仕事と介護の両立支援|当事者意識について考える
介護離職防止と仕事と介護の両立支援|当事者意識について考える2024/12/02
-
 仕事と介護の両立支援はキャリア支援です|キャリア面談のススメ
仕事と介護の両立支援はキャリア支援です|キャリア面談のススメ2024/10/31
-
 改正育児・介護休業法を活用しよう|「義務化」を上手に利用して働きやすい職場を作る
改正育児・介護休業法を活用しよう|「義務化」を上手に利用して働きやすい職場を作る2024/09/30
-
 突発事態に備えよう|介護休暇の使い方と今からできる備え
突発事態に備えよう|介護休暇の使い方と今からできる備え2024/09/02
-
 育児・介護休業の改正|それに伴う「事業主への措置義務」を考える
育児・介護休業の改正|それに伴う「事業主への措置義務」を考える2024/07/31
-
 介護者の不幸は選択肢が見えなくなること|仕事と介護の両立における選択の仕方
介護者の不幸は選択肢が見えなくなること|仕事と介護の両立における選択の仕方2024/06/26
-
 仕事と介護の両立支援の「周知対策」の秘訣|周知徹底する2つの方法
仕事と介護の両立支援の「周知対策」の秘訣|周知徹底する2つの方法2024/06/03